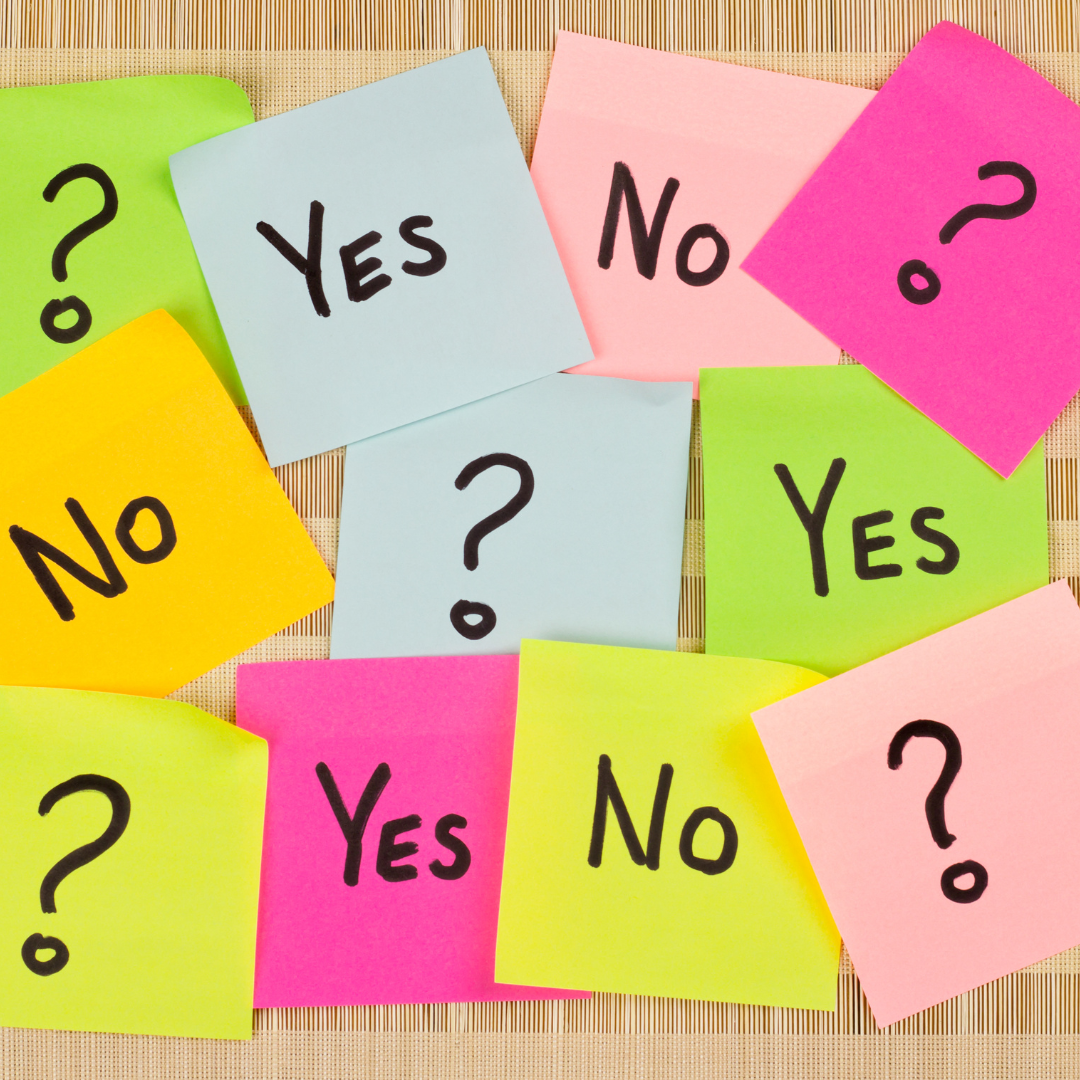
娘と城崎温泉へ、旅行しました。「城崎にて」の今回のブログ題名、文豪 志賀直哉さんにあやかりました。小説では、城崎温泉での療養を通し、生死について深く考える…という内容だったかなと。
美味しい料理をたらふく食べ、昼間からビールを飲み、マリンワールドで目一杯遊び、開催していた劇祭を堪能して帰ってきました。確かに、生きる喜びを感じた城崎温泉です。志賀直哉さんの伝えたかった想いを感じたような旅です。(ちょっと盛っています)
---
今月、第57回社会保険労務士試験の合格発表がありました。合格率5.5%とのこと、難しい試験です。
合格された皆様、おめでとうございます。惜しくも涙を流された方は、年内はゆっくりしてほしいと個人的には思います。
私自身、4回目のトライで合格となりました。負け惜しみ90%込めて言うと、1回で合格しなくてよかったなと思います。時間や費用、かかった労力を考えると膨大なものがありますが、知識の定着や自分を律する力は、その歳月がもたらしてくれたものだと思います。
社労士試験は、10科目を一度で合格しなければいけません。出題される内容を、試験当日初めて目の当たりにすることもあります。なので、社労士試験は、がんばった人だけが挑戦のチケットを手に入れられる、運ゲーのようなものだと、今は思います。
もし、悔し涙を流した人も、懲りずにまた挑戦していただけたら、とても嬉しいです。
社労士になって、
「なぜ社労士になろうと思ったんですか?」と聞かれることがあります。
正直なところ、
子育てがひと段落して、『事務 パート』で検索して一番近所で採用してもらった会社がたまたま社労士事務所で、働いていたら楽しい職業だったから。
が理由です。
確かに社労士になるためには、先述したように、時間と費用、膨大な労力というデメリットはありますが、単純にそれを超えるメリットが上回っただけです。
一方で、なぜ社労士にならないの?と聞かれたことは、ほとんどありません。
社労事務所に勤めている人であれば、社労士という選択肢は、顕在・潜在意識問わず、あるはずです。
その上で、「社労士にならない」と選択をしている人、「社労士になる」と選択をしている人。
同じ選択・決断をしているけれど、マイノリティの決断をした方にだけ、「なぜ?」と疑問を持つことは不思議だなとも思います。
行動をしなかったこともまた、『行動をしない』というその人の決断です。
経営学者の楠木建さんの記事を読んだとき、印象深かったことです
何をやるかより、何をやらないか決めること。「北へ行こう」と決めるのなら、「南にも、東にも、西にもいかない」と決めること。そこに「あるもの」ではなく、「ないもの」に本質が現れる。
行動をおこすこと、目の前にある現象にだけではなく、しないことや当たり前に過ぎていくことにも、自ら決断をしてく力を養いたいなと思います。
人生の責任者は、自分であること。
新卒で働いているときの話。お客様にスケジュール調整が上手くいかず、アポイントを変更していただいたことがあります。「予定がはいってしまい…」と説明と謝罪をして電話を切った後、
上司に「予定が勝手に入るわけないだろう。予定を入れたのは君だろ!」とこっぴどく叱られた記憶があります。
当時は、「こまけぇー!」と思っていたけれど(ごめんなさい、たくさん教えてもらった上司です。)、すべての事象の決断と責任、主体性に生きることの大切さが、今頃になり痛感します。
娘が、髪の毛を刈り上げたいと、美容院に行きました。自分で画像を検索し、決断をしている姿を見て、たのもしいなぁと、親として、彼女の「したい!」や決断を尊重できるようになりたいなと思いました。
一方で、「ポニーテールの所、三つ編みにして~!」と言ったときには、
「え…ちょっと待ってよ、ラーメンマン知ってる?先生がお母さん以上の年齢なら、『あれ、今日ラーメンマンいる』と思って、授業集中できるか不安かもしれんなぁ。この画像見て?三つ編みしたら、ほぼこの画像のラーメンマンかモンゴルマンやん」と、止めに入っている自分がいました。まだまだ修行が足りません。
でも、決断に対して、リスクを伝えることも大切かも。
ちなみに、ラーメンマンの画像を見た娘は、「やっぱポニーテールでいいわ!」と言って、元気に学校に行きました。




